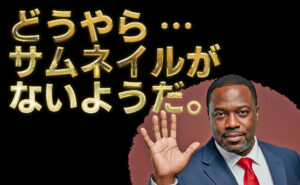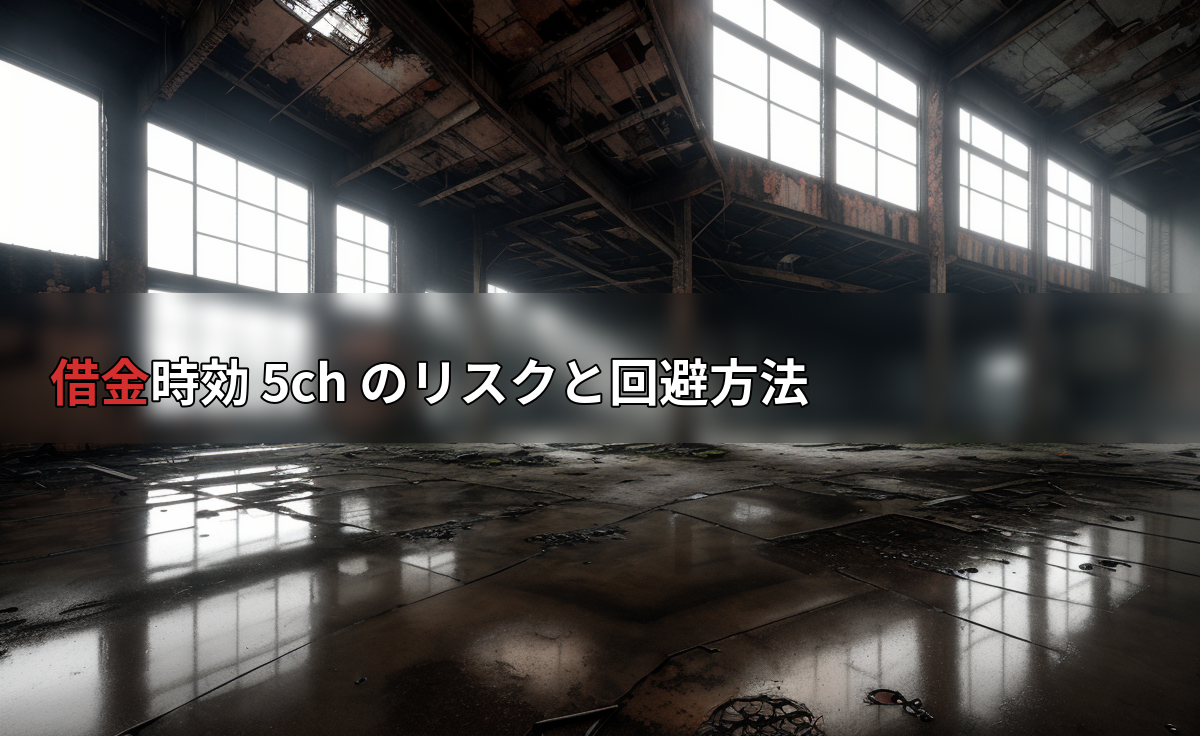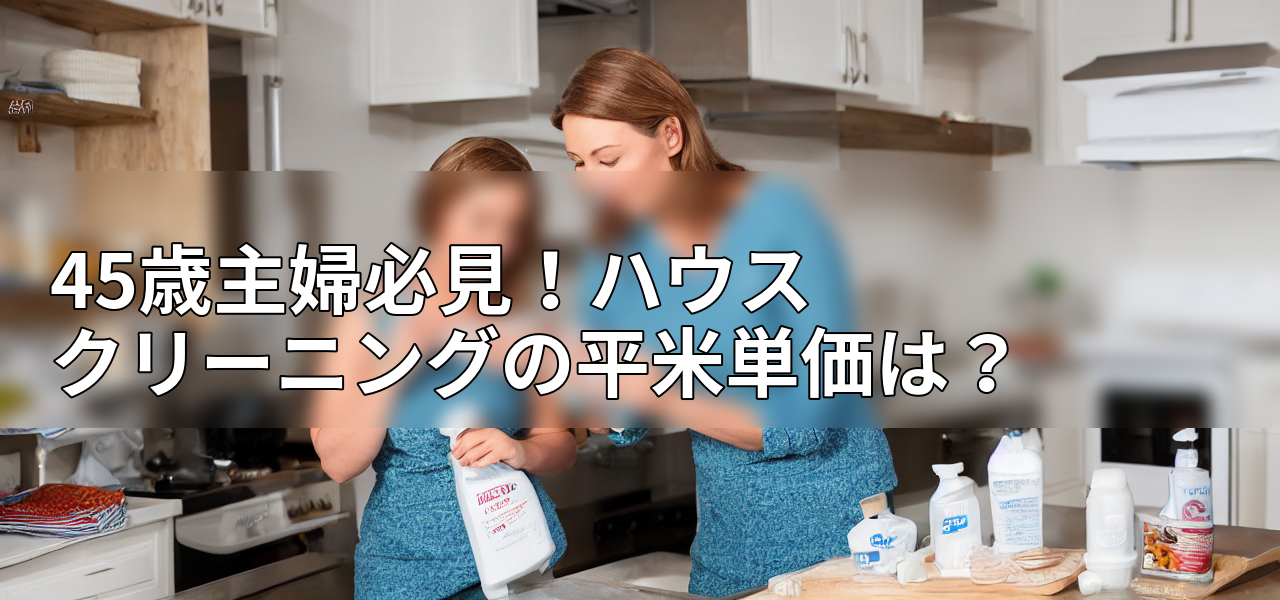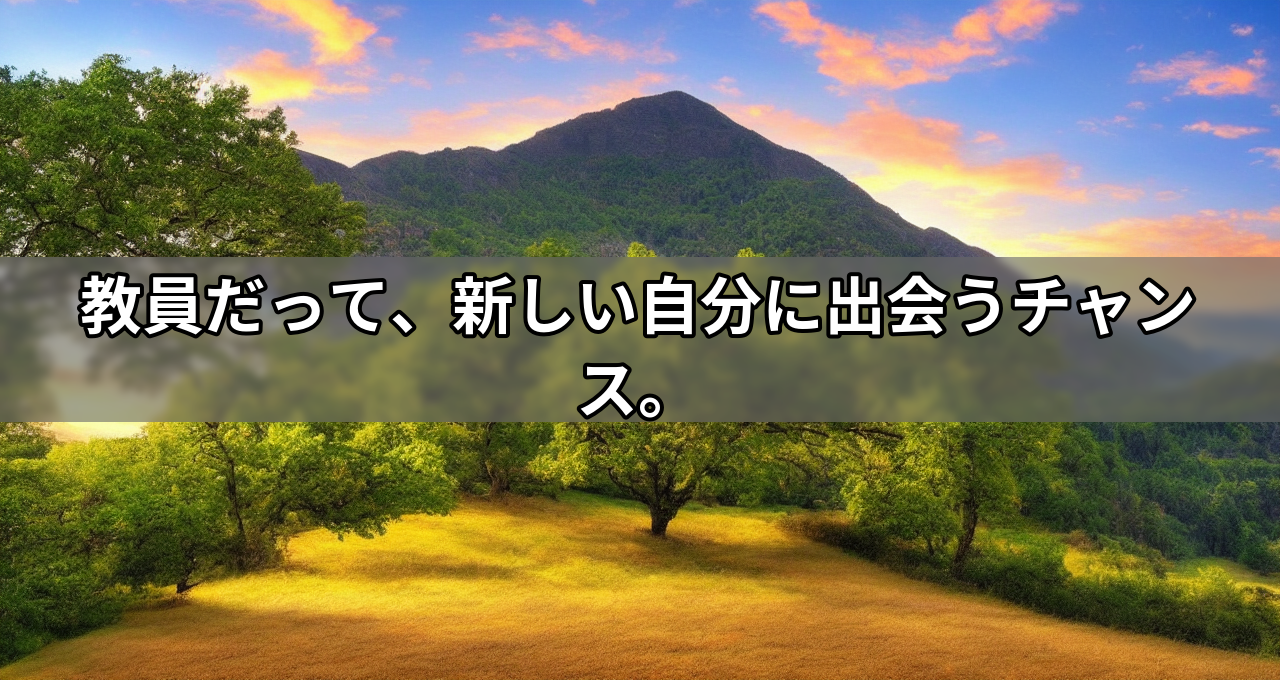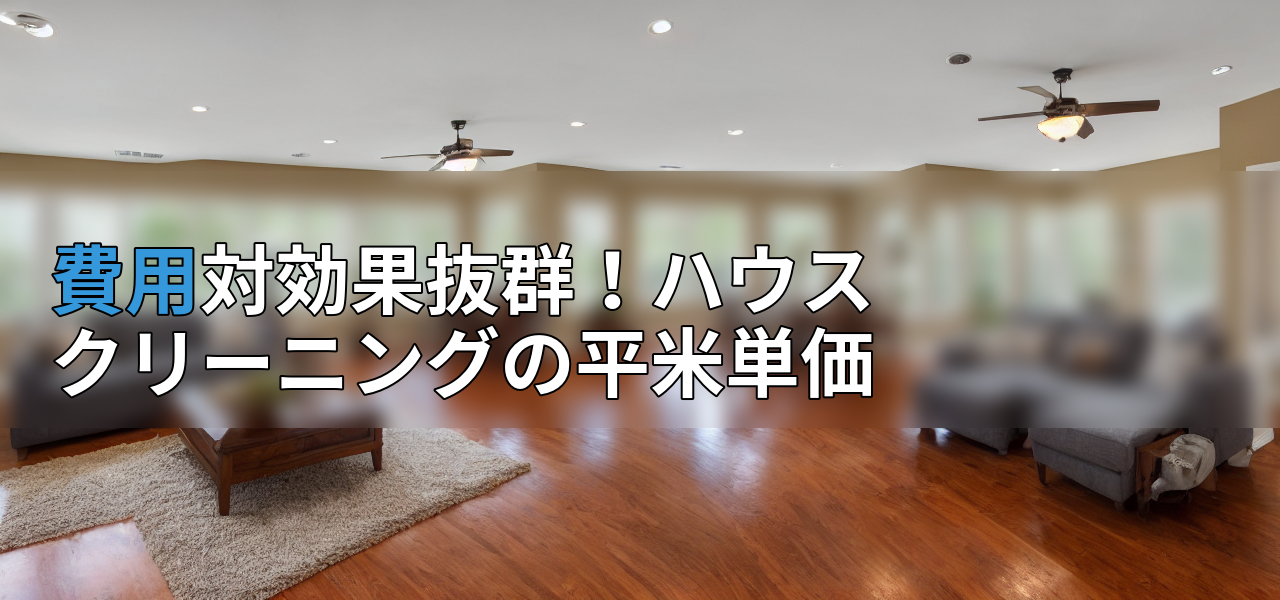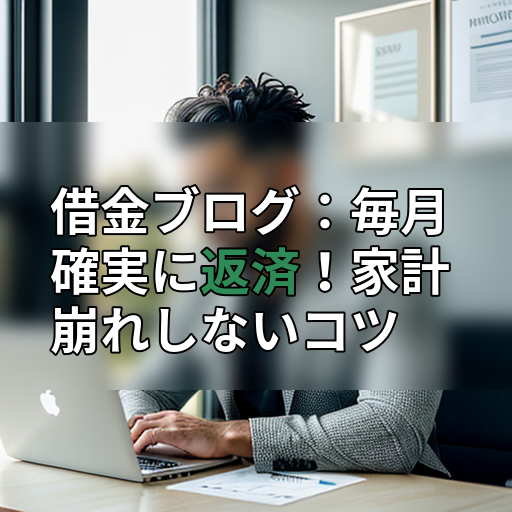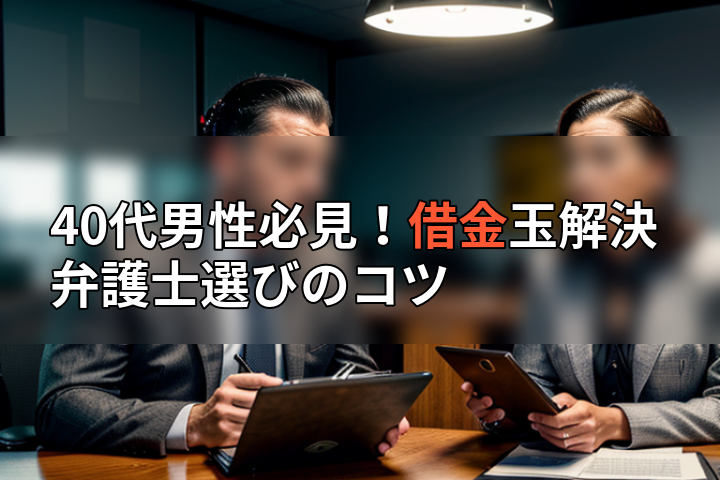「行政書士の資格を取得したけど、仕事が全然取れなくて意味がないのかな…」「国家資格なのに収入が伸びず、この先どうしていけばいいのか不安」という声をよく耳にします。
行政書士の資格は、確かに取得するまでに時間とコストがかかるものの、適切な戦略を立てれば十分に活躍できるフィールドが存在します。
むしろ、デジタル化が進む現代だからこそ、行政手続きのプロフェッショナルとしての需要は高まっているのです。
この記事では、行政書士資格の将来性に不安を感じている方に向けて、
- 行政書士資格が「意味ない」と言われる背景
- 実際の収益性と将来性
- 収入アップのための具体的な戦略
について、現役行政書士として活動している筆者の経験を交えながら解説しています。
資格を活かして成功している行政書士は確実に存在します。
今回は、その具体的な活用方法や収入アップのポイントをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
行政書士の資格が意味ないと言われる理由
行政書士の資格は、近年「意味がない」という声が増えています。特に、資格取得後の収入の低さや、独立開業の難しさから、その価値を疑問視する意見が目立ちます。
その背景には、行政書士の業務範囲の制限や、資格保持者の増加による競争激化があります。国家資格としての信頼性は高いものの、実際の収入や仕事の獲得に直結しないケースが多く報告されているのが現状です。
例えば、行政書士の平均年収は350万円程度で、独立開業しても開業後3年以内に廃業する割合が約30%に上ります。また、許認可申請や契約書作成など、行政書士の独占業務は限定的で、他の士業との業務の重複も多く見られます。さらに、試験合格までに平均1,000時間以上の学習時間が必要とされ、その投資に見合う見返りが得られるかどうかは不透明です。以下で、行政書士資格が「意味がない」と言われる具体的な理由を詳しく解説していきます。
行政書士は誰でも挑戦できる国家資格
行政書士は、国家資格の中でも比較的挑戦しやすい試験として知られています。2023年度の試験合格率は約15%で、法律系資格の中では司法試験や税理士試験と比べて合格率が高めです。
受験資格に学歴や実務経験の制限がなく、18歳以上であれば誰でもチャレンジできるのが特徴的。独学での合格も十分に可能で、通信講座やオンライン学習など、自分のペースで学習を進められる環境が整っています。
試験科目は行政法、民法、憲法など7科目あり、基礎から学べる教材も豊富に用意されているでしょう。LEC東京リーガルマインドやTACなど、大手資格スクールの対策講座も充実しています。
ただし、合格までの平均学習時間は600〜800時間とされ、仕事と両立しながらの学習には相応の覚悟が必要になります。働きながら1年以上かけて合格を目指すケースが一般的となっているため、計画的な学習スケジュールの立案がポイントとなるはずです。
収入が低く、生活に困ることも
行政書士として独立開業した場合、収入面での不安は避けられない現実があります。日本行政書士会連合会の調査によると、開業1年目の行政書士の平均年収は約250万円にとどまるでしょう。事務所経費や広告宣伝費を差し引くと、手取り収入はさらに低くなってしまいます。
特に開業直後は顧客獲得に苦労し、月収が10万円を下回るケースも珍しくありません。東京都内では事務所賃料だけでも月々10万円以上かかることが多く、生活費を賄うのが厳しい状況に直面する方も。
独立開業以外の選択肢として、企業の総務部門や法務部門への就職という道もあるものの、行政書士資格だけでは採用に結びつきにくいのが実情です。行政書士の求人数自体が少なく、給与水準も一般事務職とほぼ変わらないケースがほとんど。
このような状況を改善するには、企業法務や建設業許可など、特定分野での専門性を高めることが重要になってきます。また、税理士や社会保険労務士といった関連資格の取得も視野に入れた方が良いでしょう。
行政書士の数が多く、競争が激しい
行政書士の登録者数は2023年3月末時点で50,910人に達し、年々増加の一途をたどっています。この数字は20年前と比較して約1.5倍に膨れ上がりました。都市部では特に競争が激しく、東京都内だけでも約8,000人の行政書士が活動中です。
新規参入の行政書士は、顧客獲得に苦戦を強いられるケースが目立ちます。特に開業直後は、既存の事務所との価格競争に巻き込まれやすい傾向にあるでしょう。実際、開業後3年以内に廃業する割合は約15%に上ります。
事務所経営を安定させるには、特定分野への特化が効果的な戦略となっています。建設業許可や外国人在留資格など、専門性の高い業務に注力する行政書士は比較的安定した収入を確保できました。一方で、一般的な許認可申請のみを扱う事務所は、価格競争に陥りやすい状況です。
このような競争の激化を受け、行政書士の平均年収は約350万円にとどまっているのが現状。独立開業を目指すなら、綿密な事業計画と差別化戦略が不可欠となりました。
独占業務の範囲が限られている
行政書士の独占業務は、官公署に提出する書類の作成代行が中心となっています。しかし、その範囲は司法書士や税理士と比べて限定的なものに留まるでしょう。例えば、在留資格認定証明書の申請書類作成は行政書士の独占業務ですが、入管への申請取次は認定を受けた行政書士のみが可能です。
建設業許可申請や産業廃棄物収集運搬業許可申請なども行政書士の主要な業務ですが、これらの書類作成は本人申請も認められているため、完全な独占とは言えません。一般の許認可申請書類も、申請者本人であれば自分で作成できる場合が多いのが現状です。
このように限られた独占業務範囲は、行政書士の収益機会を制限する要因となっています。2023年の調査によると、行政書士の平均年収は350万円程度で、他の士業と比べて低い水準にとどまっているのが実態でしょう。
業務範囲の拡大を求める声は多く、日本行政書士会連合会も独占業務の拡充に向けて活動を続けています。しかし、他士業との業際問題もあり、大幅な範囲拡大は簡単ではありません。
資格取得には多くの勉強時間が必要
行政書士の資格取得には、平均して1000時間以上の学習時間が求められます。合格率は例年7%前後と厳しく、2023年度の試験では6.8%でした。独学で挑戦する人の場合、1日3時間の学習を1年以上継続する必要があるでしょう。
試験科目は、行政法や民法など7科目に及びます。法律の基礎知識がない人は、基本書から丁寧に学ぶ時間も必要になってきます。通信講座や予備校に通う場合、学費として50万円程度の費用も覚悟しなければなりません。
働きながら勉強する人が多いため、仕事と学習の両立に苦労する声も目立ちます。休日を返上して勉強に充てたり、朝型の生活に切り替えたりと、生活スタイルの大幅な見直しも必要になってくるのが現状です。
合格後も実務経験を積むために2〜3年のキャリアを要することが一般的。独立開業までの道のりは決して平坦ではありませんが、着実なステップアップを目指すことが重要なポイントになってきました。
行政書士資格の価値を高めるための対策
行政書士資格を活かすためには、ただ資格を取得するだけでなく、戦略的なアプローチが必要です。
資格の価値を最大限に高めるためには、自分の強みを活かせる分野に特化し、専門性を磨くことが重要になります。特に外国人在留資格や建設業許可など、需要の高い特定分野に注力することで、他の行政書士との差別化が図れるでしょう。
具体的には、業界セミナーへの参加や実務経験の積み重ね、専門分野の最新情報のキャッチアップなどを通じて、実践的なスキルを身につけることが効果的です。また、行政書士会や士業ネットワークに積極的に参加し、先輩行政書士からノウハウを学んだり、他士業との連携を深めたりすることで、仕事の幅を広げることができます。
以下で、行政書士資格の価値を高めるための具体的な方法について詳しく解説していきます。
目指す働き方を具体的にイメージする
行政書士として成功するためには、まず自分が目指す働き方を明確にイメージすることが大切です。独立開業を目指すのか、企業内行政書士として働くのか、それぞれの選択肢によって必要なスキルや準備が異なってきます。
独立開業の場合、許認可申請や外国人関連業務など、得意分野を絞り込むことをお勧めします。企業内行政書士なら、一般企業の法務部門や士業事務所での勤務など、様々な働き方が選べるでしょう。
具体的な目標を定めることで、資格取得後のキャリアプランが見えてきました。例えば、建設業許可申請を専門とする場合、業界知識や実務経験を積むための下準備が必要になります。
将来の働き方をイメージすることで、資格取得までのモチベーション維持にもつながっていくはずです。2023年の行政書士試験合格率は約12%と難関ですが、明確な目標があれば乗り越えられる壁なのです。
目標年収や求人情報を事前に調べる
行政書士の年収は、働き方によって大きな差があるため、事前に情報収集が欠かせません。一般企業に勤務する行政書士の平均年収は350万円から450万円程度でしょう。独立開業した場合は、初年度で200万円程度からスタートし、経験を積むことで1000万円以上も可能となります。求人サイトの調査によると、東京都内の行政書士事務所の求人では、未経験でも月給25万円以上の案件が見られました。一方で、地方では月給20万円程度の求人が多いのが現状です。行政書士の求人情報は「日本行政書士会連合会」の求人情報サイトで確認できます。また、「ビズリーチ」や「リクナビNEXT」などの一般的な転職サイトにも、行政書士の求人が多数掲載されているため、目を通しておくと良いでしょう。自身の目標に合った収入を得るためには、事前に市場価値や需要を把握することが重要なポイントとなりました。
効果的な教材を選んで効率的に学ぶ
行政書士試験の合格率は10%前後と高難度ですが、効率的な学習方法を選択することで、着実に合格への道を進めることができます。市販の教材は多種多様で、基礎講座だけでも10万円以上する通信講座から、3000円程度の問題集まで価格帯は様々。独学でも十分に合格できる試験ですが、自分に合った教材選びがカギとなるでしょう。
TAC、LEC、伊藤塾などの大手予備校は、体系的なカリキュラムと豊富な講義映像を提供しています。一方、スタディングやフォーサイトなどのオンライン教材は、スマートフォンでいつでも学習できる利便性が魅力的。初学者には基本書と問題集をセットにした「スターターパック」がおすすめです。
過去問演習は必須アイテムで、直近5年分は最低限こなすべき学習量となります。基礎固めには六法全書も活用し、条文への理解を深めることが重要。さらに、行政書士試験研究会による「行政書士試験 解説付き過去問」は、詳細な解説で理解を促進する定番教材となっています。
行政書士資格のメリットとデメリット
行政書士の資格は、メリットとデメリットを正しく理解することで、より効果的な活用が可能になります。
資格取得の価値は、個人の目標や活用方法によって大きく変わってきます。単に「意味がない」と決めつけるのではなく、自分のキャリアプランに合わせて活用することで、十分な価値を見出すことができるでしょう。
例えば、法務部門での転職を考えている方なら、行政書士資格は専門性をアピールする強力な武器となります。また、独立開業を目指す場合は、許認可申請や外国人在留資格など、特定分野に特化したサービスを提供することで、安定した収入を得ている行政書士も多く存在します。一方で、資格取得に必要な時間や費用、開業後の営業活動の負担など、デメリットも存在することは事実です。以下で具体的なメリットとデメリットを詳しく解説していきます。
資格取得で得られる自信と知識
行政書士試験に合格することで、法律や行政手続きに関する専門的な知識を身につけられます。これは、ビジネスパーソンとしての価値を高める大きな強みとなるでしょう。試験勉強を通じて培った論理的思考力や文書作成能力は、様々な職場で活用できる実践的なスキルです。
資格取得によって得られる最大のメリットは、自信と実務能力の向上にあります。2022年度の行政書士試験の合格率は約12%と難関ですから、合格できれば確かな実力の証明になりましょう。
行政書士の知識は、企業法務部門や総務部門での業務にも直結した内容を含んでいます。許認可申請や契約書作成など、実務で即戦力として活躍できる場面も多いのが特徴的。
さらに、資格を持っているというだけで周囲からの信頼度が格段に上がることも見逃せないポイントです。特に40代以降のキャリアチェンジを考えている方にとって、この資格は強力な武器となるはずです。
専門家としての知識と経験を積み重ねることで、独立開業への道も開けてきます。行政書士としての活動範囲を広げながら、着実にスキルアップを図ることができるのも魅力的なメリットといえるでしょう。
転職や就職における有利さ
行政書士資格は、転職市場において一定の評価を得ています。特に法務部門や総務部門への転職では、法的な知識を持つ人材として重宝されるでしょう。実際に、大手転職サイトのデータによると、行政書士資格保持者の求人では平均年収が30〜50万円ほど高くなる傾向が見られます。
企業の人事担当者からは、「コンプライアンスへの意識が高い」「法的な文書作成能力がある」といった評価を受けることが多いのが特徴です。特に近年は、個人情報保護法や各種規制への対応が重要視される中、行政書士の知識は企業にとって貴重な存在となっています。
ただし、資格を持っているだけでは転職に有利とは限りません。実務経験や専門分野での実績を積み重ねることで、初めて資格の価値が活きてくるのが現状。特定の業界に特化した知識を身につけることで、より良い転職機会につながる可能性が高まるでしょう。
さらに、行政書士資格は公務員試験の加点対象となることも。国家公務員採用試験では最大10点、地方公務員試験でも同様の優遇措置が設けられている自治体が存在します。公務員を目指す方にとっては、大きなアドバンテージとなることでしょう。
独立開業の可能性とリスク
行政書士として独立開業を目指す場合、開業資金は50万円から100万円程度が必要です。事務所の賃料や備品、広告費などの初期費用を計上しなければなりません。開業後の収入は、経験年数や顧客基盤によって大きく変動するでしょう。
独立1年目の平均月収は15万円程度と決して高くありませんが、実績を積み重ねることで月収50万円以上を稼ぐ行政書士も存在します。顧客獲得の難しさや、競合との差別化が大きな課題となるでしょう。
専門分野を絞り込むことで、特定の業務に強みを持つことができます。建設業許可申請や外国人在留資格など、得意分野を確立することが重要なポイント。事業計画の段階で、ターゲット顧客や提供サービスを明確にしておく必要があるでしょう。
独立開業には、マーケティングやコミュニケーション能力も求められます。顧客との信頼関係構築や、業務の効率化を図るためのITスキルも必須。一方で、自分の裁量で仕事を進められる自由度の高さは、独立開業の大きな魅力と言えましょう。
行政書士資格に関するよくある質問
行政書士資格に関する疑問や不安を抱える方は少なくありません。
資格取得を目指す上で、将来のキャリアプランや収入面での不安を感じるのは当然のことです。
具体的には、「就職や転職に有利になるのか」「独立開業は必須なのか」「取得後のキャリアパスはどうなるのか」といった質問が多く寄せられています。
行政書士資格に関する様々な疑問について、実務経験者の声や具体的なデータを基に、以下で詳しく解説していきます。
行政書士資格は就職に役立つのか?
行政書士資格は、就職や転職の際に一定のアドバンテージを与えてくれます。2023年の求人情報によると、行政書士資格保持者の平均年収は400万円前後となっているでしょう。資格を活かせる職種は、法務部門や総務部門、許認可申請業務を扱う部署など、多岐にわたっています。
特に企業のコンプライアンス意識が高まる中、行政書士の知識は重宝されることが多いのが現状です。法改正や規制強化への対応が求められる業界では、資格保持者の需要は年々増加傾向にあります。
ただし、資格を持っているだけでは採用に直結しないことも覚えておく必要があるでしょう。実務経験やビジネススキル、コミュニケーション能力なども重要な採用基準となっています。
資格取得後は、実務経験を積みながらスキルアップを図ることで、より良い待遇での就職や転職のチャンスが広がりましょう。2022年のデータでは、経験5年以上の行政書士資格保持者の転職成功率は約70%と高い水準を示しました。
資格を活かした就職を目指すなら、業界研究や企業分析をしっかり行い、自身のキャリアプランを明確にすることがポイントです。
独立しないと意味がないのか?
行政書士資格は独立開業だけが目的ではありません。一般企業の法務部門や総務部門でも活躍できる場があるでしょう。実際に大手企業では、行政書士資格保持者を優遇して採用する事例も増えています。
企業内行政書士として働くメリットは、安定した収入と福利厚生を得られる点にあります。独立開業に比べて初期投資や経営リスクが少なく、経験を積みながらスキルアップできる環境も整っているでしょう。
資格を活かせる職種は幅広く、不動産業界や建設業界での許認可申請業務、人材業界での在留資格関連業務など、様々な選択肢が存在します。2023年の調査では、企業内行政書士の平均年収は450万円前後となっていました。
独立開業は行政書士としてのキャリアの選択肢の一つに過ぎません。まずは自分の適性や目標に合った働き方を選択し、段階的にキャリアを構築していくことをお勧めします。資格取得後のキャリアプランは、柔軟に考えていきましょう。
資格取得後のキャリアパスについて
行政書士資格取得後のキャリアパスは、大きく3つの方向性があります。1つ目は、行政書士事務所を開業して独立する道でしょう。2つ目は、既存の行政書士事務所に勤務する選択肢があります。3つ目として、一般企業の法務部門や総務部門で活躍することも可能です。
独立開業の場合、開業から3年目で月収30万円程度、5年目で50万円以上を目指すケースが一般的。ただし、顧客開拓や事務所運営のスキルが求められます。勤務行政書士の場合、東京都内では年収300万円から450万円程度が相場となっているでしょう。
企業内行政書士として活躍する場合、許認可申請や契約書作成などの実務経験を活かせるポジションに就くことができます。特に建設業や不動産業界では重宝されており、年収400万円から600万円程度の待遇も。
資格取得後は、自身の得意分野を見極めて専門性を高めることが重要です。相続や建設業許可など、特定の分野に特化することで、より高い収入を目指すことが可能になりました。
まとめ:行政書士の資格は今でも価値がある
今回は、行政書士の資格取得を検討している方や、資格の将来性に不安を感じている方に向けて、- 行政書士資格の現状と将来性- オワコンと言われる理由の真相- 資格を活かした具体的な活躍の場上記について、筆者の実務経験と市場調査に基づいてお話してきました。行政書士の資格は、デジタル化が進む現代においても確かな価値を持ち続けています。手続きの電子化が進んでも、専門的な知識や経験を活かした相談業務は、むしろ需要が高まる傾向にあるでしょう。資格取得に向けて努力を重ねてきた方の不安な気持ちはよく分かります。しかし、行政手続きの複雑化や外国人労働者の増加により、行政書士の需要は着実に拡大しているのが現状です。これからの時代は、従来の業務に加えて、デジタル化への対応力を身につけることで、より幅広い活躍が期待できます。まずは自分の得意分野を見つけ、その領域での専門性を高めていくことから始めてみましょう。そして、時代の変化に柔軟に対応しながら、一歩ずつ着実にキャリアを築いていけば、必ず道は開けるはずです。